


2010年に「花に眩む」で第9回女による女のためのR-18文学賞読者賞を受賞してデビューして以来、読者が身近に感じる現代人を主人公にした小説から、幻想的な要素を含んだ作品まで幅広く執筆してきた彩瀬まるさん。常に進化し続ける彼女の、創作の裏側とは。
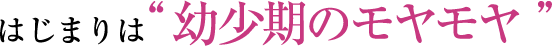

──彩瀬さんが初めて小説を書いたのは、中学生の時だったとか。
彩瀬:そうです。ずっと本を読むことも好きでしたが、絵を描くことも好きで、中学では美術部に入ったんです。楽しかったけれど、同じ部に日本画家の息子さんが先輩にいて、作っているものが明らかに違っていて。ああ、絵の方面では一生敵わないと思い、じゃあ別のことで好きなものはなんだろうと考えた時に小説だなと思いました。それで1年生の時か2年生の時に、書き始めたんです。
──最初に書いたのは、どんな小説でしたか。
彩瀬:そのころ、『ロードス島戦記』や、講談社X文庫ホワイトハートの流 星香さんの作品など、巻数の多い壮大なファンタジーを片っ端から読んでいたので、違和感なく自分もそういう小説を書き始めました。人々の背中に生まれた時から神話に基づいたあざがあって、それによって身分が決まってしまう世界の話でした。感熱紙でプリントアウトしてバインダーに綴じ、絵の巧い先輩が描いてくれたキャラクターたちの絵もつけて、学校で回し読みしてもらっていました。主人公がその世界の王様である自分の父親を殺しに行くことになる展開で、結局400枚くらいまでいきました。高校生になっても書ける時に書き進めていたんですが、だんだん、その社会を幸せな状態にするにはどうしたらいいのか悩むようになったんですよね。あざを消せば平等になるのか、平等って一体何なのか、分からなくなって書けなくなってしまったのが高1か高2のころでした。
──そのころ、将来作家になりたいと思っていましたか。
彩瀬:まったく思っていなくて、完全に趣味として書いていました。そのころはまだ、書店に並んでいる本の向こう側に作家や編集者という人たちがいることが想像できていなかったんですよね。

──ところで、彩瀬さんは帰国子女ですよね。
彩瀬:はい。4、5歳のころから2年間、アフリカのスーダンの首都ハルツームにいて、その後9歳までアメリカのサンフランシスコに住んでいました。
最初にファンタジー小説を書いたのは、その経験の影響が大きかったです。ハルツームにはイギリスの植民地時代の建物が残っていて、私たち家族や外国から駐在している人たちは、そうした大きな建物に住んでいました。でも周囲の家は、屋根がなかったり、土壁が崩れていたりしている。うちにはドライバーさんとハウスクリーニングの人と私の子守りもしてくれるメイドさんがいて、でもすぐ外にはストリートチルドレンがいる。それがなんだかつらくて、自分がどれだけのリソースを持って生まれてくるかはランダムなこと、無作為なことだなあというのを5歳くらいからずっと考えていたんです。それで中学生の時に、そのモヤモヤした感情を小説に落とし込んだら糸口が見えると考えたように思います。ファンタジー小説って、実際の社会の写し絵としてその世界をつくって、思考実験に使うことってあるじゃないですか。それでお話を作りやすかったんだと思います。
──日本語で苦労したことはなかったですか?
彩瀬:海外でも家族とは日本語で話していましたし、日本人学校にも行っていましたから、困ったりはしませんでした。小学校4年生の時に帰国してからは帰国子女用の学級に通い、体育や図工などだけ普通学級の子たちと一緒だったんですが、その子たちから「やたら難しい言葉を使う」といって嫌がられた記憶がありますね。それはたぶん、海外にいたころ、新しい日本語を本から憶えていたからだと思うんです。私が意識していないところで、何かしらズレがあったのかなとは思います。
でも、昔から国語は得意でした。絵を見てお話を作る課題で、クラスで一番よくできたといって賞をもらったりしていました。ほかの教科はできなくても、国語だけはできたんです。











