


高校卒業後、自費出版したデビュー作『リアル鬼ごっこ』が累計200万部を超えるベストセラーに。以来、『@ベイビーメール』『親指さがし』『パズル』などヒット作を生み、映画や漫画など次々とメディア展開もしている。
今回、山田さんが自費出版するに至った経緯や、商業作家としての心構えなどについて伺った。
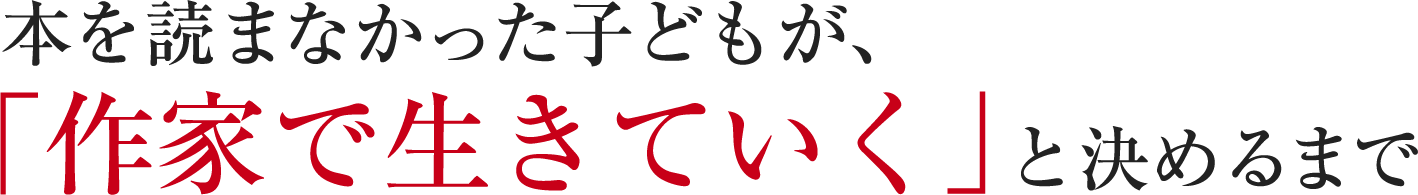

──山田さんはいつ頃から小説家を目指すようになったんですか?
山田:小説を本格的に書くようになったのは高校卒業後です。自分は何をやりたいんだろうと考えた時に、なぜか小説を書いてみたいと思ったんですよね。
早速パソコンを買って、とにかく一作書いてみようと決めました。

──それは昔から本を読むのが好きだったからですか?
山田:実は、昔は全く本を読まない子でした。ただ、頭の中で映像を浮かべながらストーリーを考えるというのは割と小さい頃からやっていましたね。
もちろん子どもですから、最初から最後まで物語を完成させていたわけじゃなくて、こういう場面があったら面白いなとか、こういう展開になったら楽しいだろうなとか。夜寝る前に空想していました。
本を読むようになったのは、小説を書くようになってからです。
当時朝から晩まで郵便局で配達のアルバイトをしていたので、夜遅くに帰ってから、机の代わりにアイロン台の上にパソコンを置いてキーボードをカタカタやっていたのを覚えてます。睡眠不足だったけど、書くのが楽しくて仕方なかったですね。
小説の書き方を誰に教わった訳でもなかったので、見よう見まねで2ヶ月くらいで一気に書き上げました。これが人生初の小説です。

──どのようなストーリーだったんですか?
山田:今思うとつまらない内容なんですけど…。すごい恥ずかしいな(笑)。
男手ひとつで子どもを育てている父親が主人公で、その子どもがある日誘拐されるんです。そして犯人から電話が来るんですけど、そこで宿題を課されるわけです。
その父親には、3人か4人の親友がいて、宿題というのは親友を1人ずつ殺せっていうもので。実は犯人はその親友の中の1人だった、という話でした。
せっかく最後まで書いたんだから誰かに読んでもらいたいなと思っていたところでちょうど自費出版の広告を目にしました。友人や親に見せるのは気恥ずかしいし、応募するレベルでもない。でも自費出版であれば編集者が見てくれるので、出版社に送ってみました。
編集者からは「本にしましょう」って言ってもらえたんですけど、話の内容だけで言ったらもっと面白いって思う作品がありますと言って送ったのが『リアル鬼ごっこ』なんです。
──それがデビュー作となったんですね。刊行から半年ほどで1万部を突破し、累計200万部を超える、自費出版本としても異例のヒットとなりました。山田さんは当時19歳だったと思うのですが、出版費用はどう捻出したんですか?

山田:出版ローンを組むことにしました。月々7万円を返済するコースだったかな。
当時、出版するにあたっては200万円かかるって話だったので、祖母に借りた50万円とアルバイトで貯めた40万円を頭金として準備しました。親からも「少し出そうか」って言われたんですけど「それは大丈夫」って断って、残りの100万円ちょっとをローンで賄いました。
200万円は19歳にとってはなかなかの額だったけど、返せない額じゃないと思って。とにかく必死に小説を書こうと決めました。

──この時すでに「作家一本でやっていこう」と思っていましたか?
山田:本を出したからといって、この業界で食べていこうとは最初は思っていませんでした。記念受験のノリですね。
これが1個実績になって何かにつながればいいなぐらいな感じだったので、変に期待することはなかったです。やっぱり作家を生業とするならば、それ相応の覚悟が必要ですしね。

──では、どのタイミングで本業にしようと思ったんですか?
山田:実は幻冬舎の編集者さんから声をかけてもらったことがきっかけだったんです。「お食事に行きませんか」って電話をもらったので、会いに行ったんです。そこで「『リアル鬼ごっこ』を文庫にしたいと思っている。それと、もし新作を考えているのであれば見てみたい」って言われて。めちゃくちゃ嬉しかったですね。
元々、いつか幻冬舎さんで本を出したいなと思っていたんです。その頃読んでいた田口ランディさんの『コンセント』や『アンテナ』の表紙が僕の中では新鮮というか斬新だったんですね。いつか本屋で平積みになっている田口ランディさんの本の横に自分の本が並んだらすごいよな、って思っていたんです。
だから幻冬舎さんから新作の話がきたときに「作家一本で挑戦してみよう」と決めて、アルバイトをやめました。











