

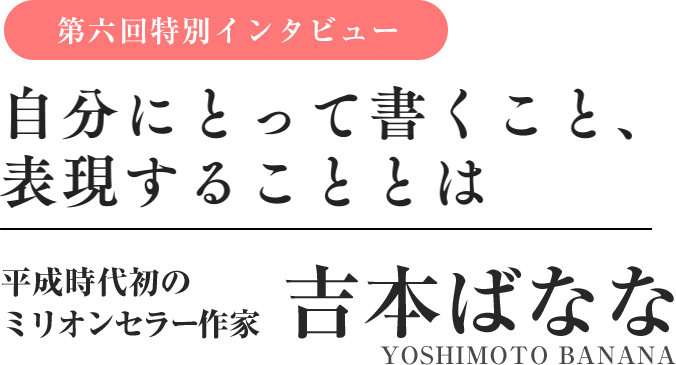
1988年『キッチン』でデビュー。昨年、作家生活30周年を迎えた吉本ばななさん。若くして、ベストセラーを連発。ブームと言われる時代をつくった作家ならではの葛藤をくぐりぬけ、今、再びみずみずしい境地に立つまでの軌跡を振り返る。




──5歳の時には作家になることを決めていたとか。早いですよね。
吉本:そうですね。7歳上の姉(漫画家のハルノ宵子さん)が絵が上手かったので「姉が絵だったら、私は文章かな」って。父(思想家で詩人の吉本隆明さん)はまだ勤めに出ていたので、ものを書く仕事を間近に見ていたというわけではなかったんですけど、本はたくさんありましたから。「出かけるというのは無理だろうな、毎日」というのも当時から思っていたので、だとすると職業の選択肢は限られてきますよね。「作家になるだろう」というより「しか出来ないだろう」ってことをわかっていたという感じです。

──処女作のタイトルは『赤い橋』。どんな小説か、覚えていますか。
吉本:決定稿が出たのが小学校4年生の時だったので、8歳か9歳くらい。ホラーっぽい冒険もので、当時から作風はまったく変わっていないですね。こういう小説を書こうという目的意識みたいなことより、もうちょっと実際的な感覚というか。作家になりたいなら、とにかく書き始めなきゃってノートに何冊分も書き続けていました。自分がどれだけポンコツかっていうのを当時からわかっていた、わかりぬいていたからだと思います。これも絶対ムリ、あれも絶対ムリ、これしかないんだったら今すぐ書くしかないだろうと。長ーい就活ですね、だから。
──幼少期に視力が悪くて片方の目だけで世界を見ていたことも、小説家としての原体験になっていますか。
吉本:結局遠くを見ないってことですよね、近眼ってことだから。手元で考えるクセはつきましたよね。それはすごく大きかったと思います。見えない方の眼を訓練するために、見える方の眼を普段は眼帯をしてふさいでいたんですよ。だから眼帯をとっちゃうと混乱しちゃうの。ものが二重に見えちゃうから。悪い方の眼を休ませるために隠した時にしか本気で本を読めなかった。外で遊ぶのも好きだったので結構忙しい子どもだったと思います。
──当時から小説の読者はいたんですか。

吉本:いなかったんですけど、ある段階から近所の友達が読んでくれるようになって。姉とか父に見せるようになったのは10代後半になってからでしたね。ひとつ書き終わったら、またすぐ次の小説を書くという今とまったく同じパターンで続けていました。書いて当然、だって仕事だからみたいな。
──当時のノートはとってありますか。
吉本:とってないです。ホントにひどいと思うので(苦笑)。日大の卒業制作で書いた『ムーンライト・シャドウ』が学部長賞をとって、人にまあまあ伝えられるんだなというのがわかって、卒業後はバイトしながら徐々に投稿していこうと思っていたら、最初に投稿した『キッチン』で「海燕」の新人賞を受賞してデビューすることになって。受賞が決まった時から「これはまずいことになった」という気持ちがありました。ストックもないし、まだ社会で何も学んでいないのにって。











