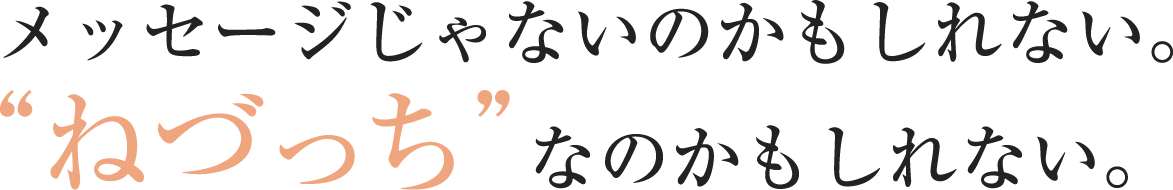

──朝井さんは現在、『小説幻冬』で短編シリーズ「どうしても生きてる」を不定期連載されています。YouTuber、派遣OL、ラッパー、保険会社の社員、Eコマース業界、介護従事者、組織ぐるみの不正……。現代の日本社会に根ざした多様な題材が盛り込まれていますが、小説の着想はどのように生まれるのでしょうか?
朝井:少し前までは、小説を書く時はまず書きたいメッセージのようなものがあって、それを最も効果的に伝えるためには話をどう組み立てればいいか、という方法論だったんですけど、最近は違ってきているかもしれません。「本質的に似ているけれど、すごく離れた場所にあるもの」を見つけた時に、小説を書く癖がある気がしています。「一見違うけど、本質的な部分までめくっていくと要素は同じだよね」みたいなものが繋がると、一気に普遍性が宿って、読み物になる気がするんです。
「どうしても生きてる」で言うと、一番顕著なのは「そんなの痛いに決まってる」(2018年12月号掲載)でしょうか。旅行とSMが似ている、とは以前からなんとなく思っていたんです。だけど、「思ったことをそのまま口に出していい気持ちよさ」が共通点だと自分なりに言語化できたときにやっと、ずるずるずるっと全体のプロットができあがるんです。だから、今の自分にとって大事なのはメッセージじゃないのかもしれない。ねづっちなのかもしれない。

──確認なんですが、ねづっちは「整いました!」で流行語大賞にもノミネートされた、お笑い芸人さんですよね? 「○○とかけて××と解きます。そのこころは?」と。
朝井:そうです。ねづっちって謎かけしてるとき、絶対気持ちいいと思うんですよ。私も「これとこれは、ひとつの言葉で繋がる。ここが本質的に一緒だ」って気付いた瞬間、ものすごく快感なんです。その快感を再現するために、小説を書いているところがあるんです。特に、短編はそう。だから「どうしても生きてる」シリーズは、私の快感の記録のようなものです。

──読み手にとっては、発見の快感がもたらされると思うんですよ。例えば1篇目の「七分二十四秒めへ」(2018年3月号掲載)は、YouTuberの「バカバカしい」動画に、「救われる」感覚が描かれていますよね。
朝井:私は2年前くらいからYouTuberの動画を観まくっているんですけど、素直に動画の内容を楽しんでいるというよりは、動画を鑑賞することで新たな自分に出会うことが楽しいんです。ただただ若者が元気に動き回る動画に対して、なぜか猛烈に傷つきながらも観るのをやめられない自分、とか。
このあいだ久しぶりに会った大学時代の友達が、今世紀最大のカミングアウトみたいな顔で「私、今年30歳だけど、けみお(※1995年生まれのYouTuber)を観てる」って言ったんです。「え? ……実は、私も」って意気投合して盛り上がったんですけど、その人も自分と全く同じ感覚で動画を観ていたんです。それは、かつて持っていたはずだけれど今は失ってしまった、「自分は自由である」という感覚を思い出させてくれるタイムカプセル的な感じで観ている、というものです。言ってしまえば高校野球とかと同じ感覚で観ているわけです。具体的に言うと、けみおや彼の友人たちって、街でいきなりおっきな声出すんですよ。街でいきなりおっきな声出せるのって、若者、というか、その街の主人公は自分だと思える人の特権だと思うんです。

──なるほど(笑)。
朝井:けみおや彼の友人たちの、ニューヨークでもパリでもハワイでも表参道でもどこでも「この世界の主人公は私たちだ!」って思えている感じが眩しすぎて、ただ輝いて見えるだけではなく目が潰れそうになるんです。だから傷つきもするんです。その感覚って、日本だけで暮らしていると、ほとんど22歳で失われると思うんです。つまり社会人一年目ですね。そのくらいから、街や店内での声のボリュームが落ちていく。自分は地球における脇役なのかも、と自覚していく。高田馬場って早稲田大学の学生ばっかりだから声でかい人ばっかりなんですけど、歩いていると、みんながみんな自分がこの星の主人公であると思ってる空気というか、パンパンに膨らんだ「人生最後の万能感」に張っ倒されそうになるんです。道もがっつり真ん中を歩いていて、端に寄らないんです。それを観ているときの感覚が心の中に溜まって溜まって溢れ出したものが集まって、「七分二十四秒めへ」という作品が生まれました。











