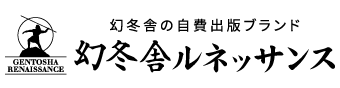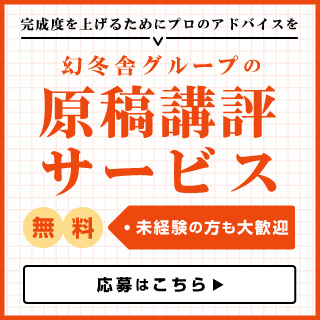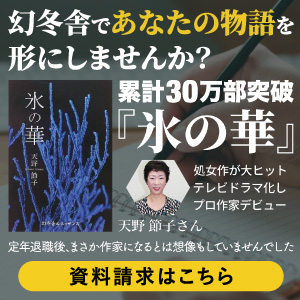1/4380 よんせんさんびゃくはちじゅうぶんのいち
本コラムでは、幻冬舎ルネッサンス宛にご応募いただいた、読者の方からの寄稿文をお届けします。どうぞご覧ください。
「蠍座 今日のラッキーカラーはグリーン。ラッキーアイテムはタンブラー。いつもと違う道を通ってみましょう。発見や電撃的に恋に落ちる事もあるかも!」
毛布に包まって目覚めのコーヒーを傾けながら、朝の情報ワイドをぼんやりと眺めていた。テレビの中のテンションの高さと、自身とのギャップを感じながら今日の段取りをなぞる。
9時、出社。新プログラムの社内ブリーフィングの後、11時〜13時まで取材。カメラマンは現地で合流だから…後でメール入れておくか…ランチは適当に…15時…新プログラム合同チームの顔合わせ…からの懇親会。
「……電撃的に恋に落ちる事もあるかも………」
リビングテーブルに雑然と積まれた新聞とDM。足下に積まれた雑誌。コーヒーを一気に飲み干すと、シャワーを浴びるべく勢いよくソファーから立ち上がった。
蔵田光。38歳。フリーライター暦8年。
大学卒業後、女性情報誌を中心に展開している編集プロダクションに就職。30になったのを機に退社。特に会社に不満はなかったが、より自分の専門を活かせる仕事に関わりたいと独立を決めた。フリーランスは厳しさもあるが、望んだ分野での仕事とつながり、今まで以上にやりがいを感じている。
読書離れ、出版不況と言われて久しいが、読書の形が変わってきているのだろう。ネット系の仕事も多く、結構慌ただしい毎日だ。
今日もネット系情報サイトの仕事。複数の企業が参加する行政系のプロジェクトだ。プロジェクト決定後、関係者全員が集まっての初めての顔合わせとなる。
プロジェクトは、地域資源を発掘、紹介しようというもので、項目も多岐に渡る。光は歴史・文化チームを担当する事になっている。大きなプロジェクトで、かつ好きな分野の担当。しかもチームリーダーという立場に少なからず緊張していた。少しの憂鬱と感傷も抱えて。
(固すぎず、砕けすぎず…なんだけど、さて、何を着ようか…)
ベリーショートの濡れ髪、首にバスタオル、下着姿。しなやかなボディラインはまだ少女のような雰囲気がただよい、それがかえって艶かしさを感じさせる。
昨日から考えていたにも関わらず、やっぱり決めきれなくて、クローゼットの前でしばしファッションショーが始まる。といっても、ゆっくり選んでいる時間もない。
紺のジャケットにクロップドパンツ。インナーは程よくフィットする白のTシャツ。足下はスニーカーにした。顔合わせ前に一本取材がある。結局無難なコーディネートになってしまったが、お役所も同席するし、いいかと納得させた。

「あ、光さん、おはようございます!」
プロダクションに出勤すると後輩の加奈芽が元気よく挨拶してきた。
「光さん、今日、カッコいい〜〜〜例のプロジェクトの顔合わせですよね?」
期待に満ちた目で見つめてくる。
「そうだけど…」
「代理店はアドエージェンシーですよね?で、桐プロも参加なんですよね?」
「あ〜…合コンとか、そういうの言い出すのやめてよね。」
「え〜〜〜?優良物件の情報と橋渡しは必須じゃないですかぁ〜〜〜」
「あんたね、合コンもいいけど!この前も締め切り前にあんたの尻拭いしたの、誰だと思ってんの?」
PCが起動するまでコーヒーでもと給湯室に向かう。
「それはそうですけどぉ〜…それとこれは話が別というかぁ」
「別じゃないっ!やる事できてからの話。迷惑かけてる私に仕事以外の事頼んでくるな。ていうか、仕事も頼んでくるな。自分で解決しろ。」
「え〜〜〜カワイイ後輩のお願いですよ〜〜?」
給湯室まで追いかけてくる。
「え〜?私、フリーの契約なんでぇ〜後輩とか〜責任ないし〜」
「光さん、今日も朝から手厳しいですね〜」
コーヒー片手にくすくす笑いながら声をかけてきたのはカメラマンの武田鉄朗。食器棚から光のマグカップを取ると、コーヒーを注いで手渡す。
「あ、ありがと。」
「お礼はデートでいいですヨ?」
「ほんっとどいつもこいつも朝から冗談きついわ〜。」
「やだな〜光さん、こないだの現場、僕、頑張ったじゃないですか。ご褒美あってもいいと思うんですけど〜」
「ご褒美は今回のプロジェクトのカメラマン指名じゃないの。」
「そう、いいよね!武田さん!私も連れてって。」
「う〜ん、加奈芽ちゃん、まずは自分の担当、キチンと終わらせようか〜」
「え〜〜武田さんまで〜〜〜」
「ほらほら、こっちはこの後ブリーフィング。遊んでる暇ないのよ。行った行った!」
冷蔵庫を開け、ミルクを探しながら加奈芽を給湯室から追い出した。と…鉄朗が光の腰に手を回してくる。
「…武田くん、セクハラで訴えるよ?」
「嫌ならちゃんと拒否してください。ずっと僕、真面目に告白してるじゃないですか。」
「加奈芽くらいの若い子、見なさいよ。私、この秋に38。君と8つも違うの。もう子供も期待できないし。」
「それって断る理由になりませんよね。」
おはようと編集室から挨拶を交わす声が聞こえる。
「君も諦めないね。」
「本気ですから。」
鉄朗は、光の泣きぼくろにキスすると、さっと給湯室から出て行った。抗議する間もない。
光はカフェオレにするのをやめ、ほろ苦いコーヒーを口に運ぶ。
「…電撃的に君と恋に落ちれれば良かったんだけど。」
対象がいなくなった空間にポツリと呟いた。
武田鉄朗。30歳。カメラマン兼ライター。プライベートで更新している散歩日記が受けて、30代の女性向け雑誌で小さなコーナーを担当するようになった。このきっかけを作ってくれたのは光だった。
光との出会いは5年前。結構長い。光がこのプロダクションとフリー契約する前は、企画毎の単発の仕事だったため、光との接点はあまりなかった。
当時はボブカットで、切れ長の目と泣きぼくろが色っぽいお姉さんだなと、編集室で見るのがちょっとした楽しみだった。
しかし、光と組んで仕事をした途端「年上の綺麗なお姉さん幻想」は崩れ去った。
仕事に関してはとにかく容赦がないのだ。リサーチからアポ取り、取材にレイアウトと基本何でも一人でこなす。写真もプロ並ではないがポイントを理解しているので、使用に耐えうるレベル。だからこそフリーでやっていけるのだろうが、同じレベルを要求されるとキツい。はっきりとしたものいいも、綺麗なだけに刺さるのだ。
(最初の印象と違う。こりゃ、30過ぎても独身のはずだよ…)
最初の淡い憧れはどこへやら…いつの間にか光は鉄朗の苦手な同僚ナンバー1になっていた。
しかし、先輩達の光への信頼は厚い。時折、仕事終わりに何人かと連れ立って楽しそうに呑みに出かける姿も見かけた。
ちょっと色っぽいかもしれないけど、あんなキツいだけの女のどこがいいんだろうと、鉄朗は不思議だった。
ある日、歴史を楽しむ気軽旅という企画で、よりによって光とチームを組む事になった。
東京近郊、1泊プランを3カ所取材しなくてはならない。長時間一緒にいるというのもストレスだったが、それが宿泊を伴うとなるとなお憂鬱だった。が、憂鬱に思っているのは鉄朗だけのようで、光は移動中、現地での取材とは別になにやら計画を立てている。
「武田くんさぁ、若いし、体力あるよね。」
取材へ向かう電車の中で、光がいきなりこういった。
「はぁ、まぁ、そうですね。」
「オール、いける?」
「えっと、取材の後ですか?」
「そう。」
「ま、明日押さえるのは宿周辺だけなんで、大丈夫かな。なんですか?」
「ふふふ…オールは大げさだけど、ちょっと夜更かし。機材も持ってね。」
正直、夜まで光と一緒というのは気が進まなかったが、子供のようにはしゃぐ様子は意外で、可愛く見えた。
取材は光の完璧なスケジューリングにより、順調に進んだ。順調に進むのだが…光は取材しながら自身のデジカメでいろいろ写真を撮っている。鉄朗が撮影している間に、ふらっと路地に入ってしまい、振り向くと光がいないという事が何度かあった。5分も待っていれば戻ってくるのだが、正直、ちょっと面白くない。
「光さん、言ってくれれば僕、撮りますよ?」
「あ、ごめん。自分のメモ用に撮ってるのよ。今は現物を前にしてわかっていても、会社に戻ったら忘れちゃったりするから。勝手に行動したら迷惑かけるよね?ごめんごめん、気をつける。」
あっさりと謝られて鉄朗は拍子抜けしてしまった。
夜、宿での撮影も終え、後は自由時間だ。
「さてと…武田くん、行くわよ。念のために長袖と、長ズボンでね。靴下もちゃんとはいてた方がいいな。」
「呑みに行くんじゃないんですか?」
「呑まないわよ。あ、私は運転しないし、呑んじゃおうかな?」
ふふふ…といらずらっ子の様な笑いをもらす。
「え〜〜〜?機材も持って行くんですよね?行き先はどこですか?」
「ふっふ〜秘密。まぁまぁ、いいじゃない。時間あるし。」
なんだか振り回されている気もするが、ミステリーツアーのようで面白いと思った。機材を担いで光の後に続く。
光のナビでたどり着いたのは、戦場ヶ原展望台だった。
「…は〜〜〜…凄いですね…東京の近くでこんな星空があるとは思いませんでした。」
満天の星空に圧倒されて言葉も出ない。
「今回の紙面では紹介できるかちょっと難しくて。天気次第だし。武田くんの写真があればイケルかな?ってね!」
暗がりの中、声だけというのが妙に近く、生々しく感じられた。
「ま…仕事もそうだけど、これだけの星を見れたら嫌な事も吹き飛んじゃうよね〜」
嫌な事。さらに意外な言葉に鉄朗はつい本音を漏らす。
「え?光さん、嫌な事ってあるんですか?」
「あるに決まってるじゃん!君さ、私の事なんだと思ってんの?」
「いや…なんかいつも完璧なんで…」
「完璧?ないない。いつも必死。プライベートなんて適当で、片付けられない女だもん。恥ずかしながら。」
「まさか!」
「いや、ホントだって。編集部で私の家で呑んだ事ある人たちはみんな知ってるよ〜
さて!じゃ、ここまで紹介できるように武田くん、もうちょい頑張ってくれる?お礼は今日の呑み代。」
いつもの会社を離れているせいか、はたまた星空効果なのか…光の意外な一面に触れて、これまでの苦手意識はどこかへ行っていた。
翌日の取材も無事終え、東京に戻ったが、トラブルはここで起こった。
「写真のデータがない?」
「す、すみません。撮影後、確認していたんですが、データを移そうとしたら…一部、すっぽり、ないんです。」
「どこがないの?」
「昨日の日中回ったとこ、ほとんど…」
鉄朗は真っ青になって、今にも倒れそうだ。
「わかった。時間的にも撮り直しには行けない。私がメモで撮ってたのでどうにかできる?」
大きなカットでなければどうにかなりそうだ。
「編集長に掛け合ってみましょう。」
光は鉄朗の不注意を責める事なく、星空観察を含めた代替プランを掛け合ってくれた。もちろん、大目玉を食らったが、光が一緒に頭を下げてくれたおかげで処分は免れた。免れたどころか、星空の写真を評価され、これが少しずつ大きな仕事を任されるきっかけになったのだった。
程なくして気軽旅企画は終わり、光は編集部に顔を見せる事もなくなった。
(あのお詫びもちゃんとできてなかった。)
フォローに必死で気の回らなかった自分が嫌になる。お詫びとお礼をしたいという気持ちよりも、もっと光を知りたいという気持ちが大きくなっていたから尚更だ。
(あれだけ情け深い女性がなんで一人なんだろう…)
半年後、光はフリー契約で再び編集部に戻ってきた。鉄朗にとっては運命のように思えた。
真剣につき合って欲しいと打ち明けたのは再会してすぐ。最初から受け入れてくれるとは思っていなかった。なんせ自分は8つも年下だ。光からみたらまだ鼻垂れの子供だろう。案の定断られたが、簡単に引き下がる程、軽い気持ちではなかった。断られてもアプローチを続け、気がつけば3年が経っていた。
給湯室での事を気にする風でもなく、光の振る舞いは至って普通だ。
鉄朗のちょっと強引なアプローチには訳がある。これぐらい強引にしないと隙がないからだ。
(光さん、断る時にいつも辛そうにするし…食事に誘ったら乗ってくれるし。僕の事が嫌いではないと思う。まぁ、さすがに3年も断られると凹むけど…)
鉄朗が注いだコーヒーを飲みながら資料に目を通す光を眺める。光を見ていると、心に突き刺さる小さな棘の痛みさえも甘く感じてしまう鉄朗だった。
新プロジェクトの社内ブリーフィングを終え、光は取材に出ていた。取材者も協力的で予定通りの時間に終える事ができた。
カメラマンと別れ、一人、少し遅いランチを取る。
「蠍座 今日のラッキーカラーはグリーン。ラッキーアイテムはタンブラー。いつもと違う道を通ってみましょう。発見や電撃的に恋に落ちる事もあるかも!」
オーダーを待っている間、ふと、今朝のテレビの星占いを思い出す。取材をしているときはすっかり忘れていたが、急にそわそわしてきた。
(会いたいような、会いたくないような…知ってたらこのチーム、辞退したかもなぁ…)
光は小さなため息をつく。会いたくて会いたくない相手。桐プロのカメラマン、松永雅彦だ。
松永雅彦は10歳上。今年で48になるはずだ。光が大学卒業後就職した編集プロダクションでの先輩。出会いは研修初日。簡単な入社式を終え各部署を案内されている時だった。
緊張しながら挨拶をし、目が合った途端、光と松永の間でぱちんと何かが弾けた。
(あ…!)
お互い相手が何を感じたか、わかってしまった。
(この人、私のだ…)
緊張とは違う興奮で心拍数が上がる。松永も動揺したようで、一瞬、視線が泳ぐ。
しかし、そこは松永の方が大人だった。瞬時に気持ちを立て直すと「これからよろしく」と手を差し出してきた。
握手した瞬間、また何かが弾けた。さっきよりも強烈に。快感を伴った衝撃は若い光を困惑させた。
(何?これ?ど…どうしよう…)
松永も同じく戸惑っているのが伝わってくる。息も上手く吸えない。松永はぱっと手を離すと「鉄は熱いうちに打て。せいぜいしごかれろ。頑張れよ後輩」と大げさに言葉をかけ、お互いの感覚を強引に断ち切った。
雷に打たれたように恋に落ちる。そんな夢物語なんてあるわけない。そう思っていた。その瞬間まで。
しかし、松永との電撃的な出会いに動揺したのは一瞬。その後は仕事を覚えるのに精一杯の忙しい毎日がやってきた。それは光にとって平常心を保つ、いい材料だった。
松永雅彦は元ラガーマン。大学時代に写真が趣味の友人の影響を受けて、写真を撮り始める。いつかはスポーツ系の雑誌に関わりたいと思っている。ムードメーカーでぐいぐい引っ張って行くけれど、実は繊細で、気配り上手だ。太陽の様な人だった。密かに憧れている女子社員は多かった。
社内で松永に会うと感情が揺さぶられるが、冷静でいられたのは松永が既に結婚していたからだ。三歳になる女の子の父親でもあった。後輩の面倒見のいい松永は良き夫、よき父のようで、時々子煩悩を思わせる我が子自慢を聞く事があった。お互い運命の相手と感じていても一歩踏み出さない理由はそこにあった。
そして冷静でいられたもう一つの理由は、大学からつき合っている同い年の彼氏の存在だった。
彼は公務員、光は出版業界。卒業後は違う道に進んだが、読んだ本の感想を言い合って過ごすゆるやかな休日が好きだった。
(松永さんはいい先輩。それでいい。
彼も悪い人じゃない。私の事をわかってくれてる。そろそろ結婚しようかって話も出ているし。
松永さんと何があった訳じゃないし…大丈夫、このまま上手くやっていける。)
自分の感情を説得するように何度もそう言い聞かせて、とにかく仕事に打ち込んだ。あやういバランスの上に成立している関係だったが、仕事で一緒になる事はなかったし、問題はなかった。
そのバランスが崩れたのは、光が就職して3年目の冬。松永が退職する事になった時だった。
松永は年度一杯で会社を辞め、グラビア系の編集プロダクションに移るという。そこはスポーツ系の雑誌を数本抱えていた。松永がやりたがっていた仕事だ。
松永と離れてしまうショックはあったが、一方でこれで諦めきれる、息苦しさから解放されるとほっとした光がいた。
送別会も取り乱す事なく、いい後輩として、そこにいる事ができた。松永も同じように感じているようだった。
(寂しいけど、これでいいんだ。)
送別会の間、光はずっと心の中で繰り返していた。
会がお開きになり、それぞれ松永に餞の言葉をかけ、帰ってゆく。光もこれまでの礼をいい、帰ろうとした。
「頑張れよ、オレも向こうで頑張るわ。」
陽に焼けた顔にニカッと笑顔を浮かべ、松永が手を差し出した。反射的に手を握った途端、身体中を電流が走った。衝撃に耐えきれずへたり込んでしまう。握った手から松永の動揺と後悔、興奮が伝わってきた。きっとあちらにも自分の感情が伝わっている事だろう。
(あ、ダメだ…)
光はぎりぎりの所で感情に抗った。
「どうした?蔵田!飲み過ぎたか?」
へたり込んだ光を見た同僚が引き返してくる。松永は光を支えると
「悪ぃ、もしかしてオレ呑ませすぎたかも!蔵田と同じ方面だからタクシー捕まえて送ってくわ。」
蔵田ぁ、こんな日に面倒かけてんじゃないぞ!とやいやい囃す声が遠くに聞こえる。松永が光を抱え、タクシーに乗り込む。向かった先はそれぞれの自宅ではなく、ホテルだった。
慌ただしくホテルに入ると、ものも言わず、むさぼるように何度も深いキスをした。服を脱ぐのももどかしく裸になると、お互いを確かめるように愛撫する。ただただ相手とつながりたかった。
松永を受け入れた瞬間、背骨を伝って脳髄を蕩かすような快感が駆け巡った。完全に二人の箍は外れた。何度も求めあって、最後はどっちがどっちなのか…境界がわからなくなっていた。
携帯電話が鳴っている。……いや……メールの着信音だ。
重いまぶたをこじ開けると、見知らぬ壁が見えた。ベッドサイドの時計は午前4時を指している。婀娜っぽい雰囲気に、ここがホテルだと思い出す。背中に感じる熱と、規則正しい呼吸。松永に抱きしめられている。
松永の腕からそっと抜けると、部屋中に脱ぎ散らかした服をかき集め、携帯を探し、メールを見た。彼からのメールだった。氷で心臓を掴まれたように、一瞬で強ばった。メールを確認せずにバスルームに向かう。
シャワーを浴びる。シャワーを浴びている間、震えが止まらなかった。
後悔はなかったが、松永と面と向かって別れる勇気はなかった。光は身支度を整えると、メッセージも残さず、松永を見る事もせずに部屋を出た。
松永とはあれ以来、会っていない。連絡先もホテルを出た時に削除した。
あの日の事はもちろん誰にも言っていない。墓まで持って行く二人の秘密だ。それはある意味、松永との深い絆のようで、今を連れ添う妻以上の優越感を光に与えてもいた。
(アレは夢。これから彼だけを見て、幸せになる事を考えればいい。)
光はそうできると思っていたが、松永と肌を合わせたあの一夜は簡単に忘れられるものではなかった。
あれ以来、彼を裏切った後ろめたさから、どこかぎくしゃくしてしまう。生活もすれ違う事が多くなり、程なく別れてしまった。別れは彼から切り出された。悲しさはなかった。
しかし、一生、誰にも打ち明けられない秘密を持ってしまった罪悪感は、光の中に痼りとなって残った。
あれから12年。実に12年ぶりに松永に会う。新しいプロジェクトより緊張し、憂鬱だった。
松永が別れたという話は聞こえてこない。12年経ったとはいえ、会ってしまったら感情をコントロールできるだろうか?自信がない。
結ばれる事はないと理解していたとはいえ、やはり肌を重ねた後、喪失感に苦しんだのも事実だ。もう一度あの気持ちを味わうのはキツい。
12年経ったというのに未だにあの日の感覚が甦ってくる。滑らかな肌、熱い息、滴る汗の味。未だに捕われている自分がいる。
この12年、松永以外の人を自分の中に存在させようと努力はした。何度かつき合ってはみた。が…肌を合わせると「違う」と感じてしまうのだ。比べても仕方がない、比べていないつもりなのだが、一旦そう感じてしまうと、心がこれ以上、進んでくれないのだ。
(どうせなら禿げてメタボのおじサンになってればいいのに。)
子供染みた思いつきに苦笑いする。
8歳下の鉄朗からの告白は正直驚いたが、嫌ではなかった。むしろ嬉しかった。久々に胸の奥に甘い、温かい感情が沸き立つのを感じた。
鉄朗がやたら光に触れてくるのは、精一杯のアピールだ。不快感はない。実際、光の中で鉄朗の存在は少しずつ大きくなっている。鉄朗の作戦はある意味成功している。そして鉄朗を突き放せない時点で光は負けている。
(あの熱に全てを委ねられたら…)
光の頬、うなじ、鎖骨をなでる鉄朗の手の熱、少しゴツゴツとした感触を想像する。
(でも…)と光は一歩引いてしまう。
(これまでのように、心が立ち止まってしまったら)
光は鉄朗に好意を持っている。だからこそ、拒否する事になったら辛いのだ。墓まで持って行く秘密と12年間、歩いてきた報いだった。
(あ〜あ、盛大に奥サンと子供の事、のろけてくれないかな。)
元ラガーマンの松永の事だ。禿げててもカッコいいままなんじゃないかな。それできっと相変わらずの愛妻家の子煩悩だろうし。そうでないと私の苦しい日々はなんだったのかしら?許せないな。
矛盾した思いにまた苦笑する。
と…その時、スマホが振動し、メッセージが届いた事を知らせた。妄想と感傷の世界から現実に引き戻される。
「光さん、今どこですか?車で向かうんでピックアップできますけど。」
鉄朗からだ。光への好意を隠そうとしないのも、堂々とアプローチしてきても嫌みにならないのも彼の心根の良さか…一途に光だけを見る鉄朗は正直可愛い。穏やかな気持ちになる自分がいた。
光はちょっと考えたが、居場所を伝えるべく、鉄朗に電話する。
(今日を乗り越えられたら君と向き合えると思う。)
電話を取った時の鉄朗の声に期待を掛けて、呼び出し音を聞いていた。