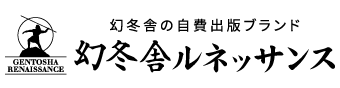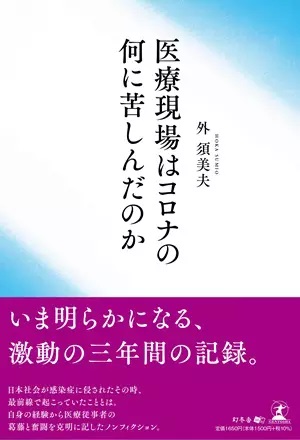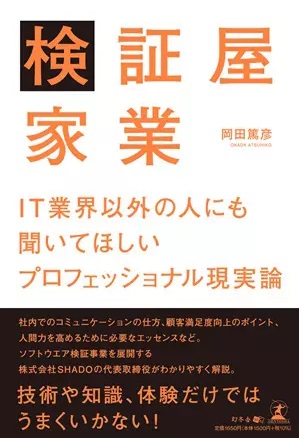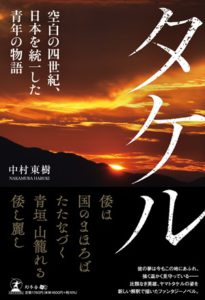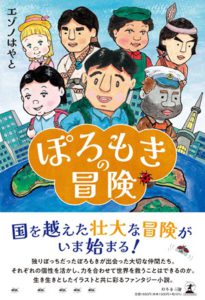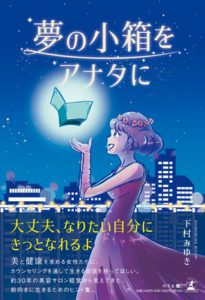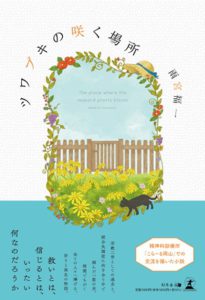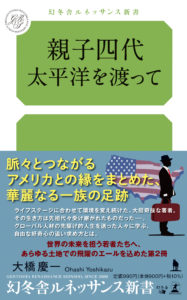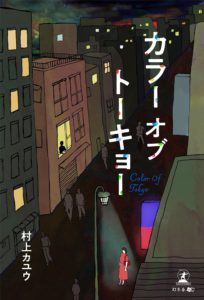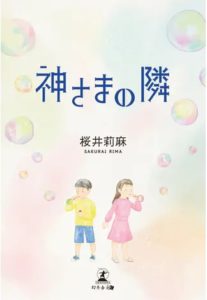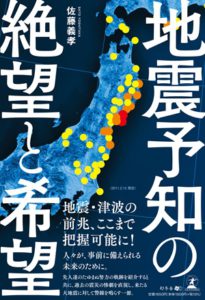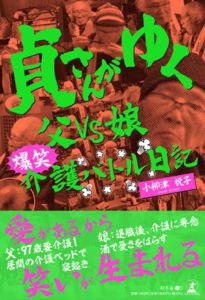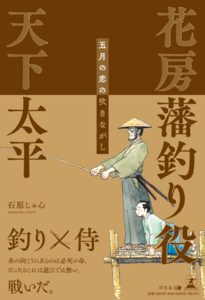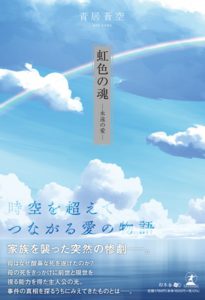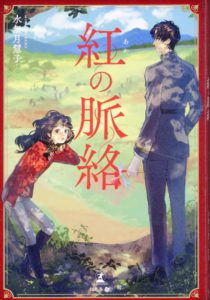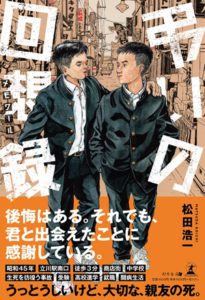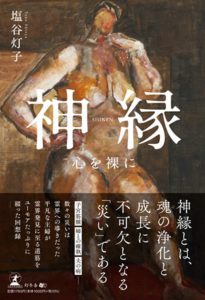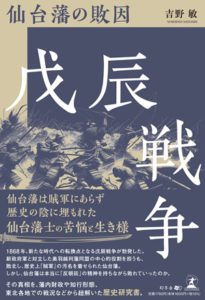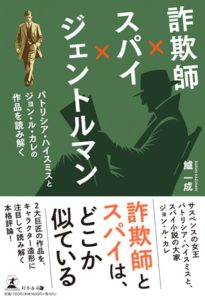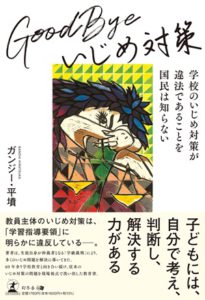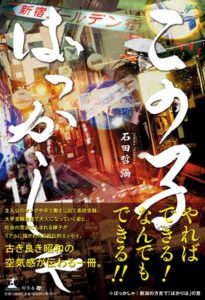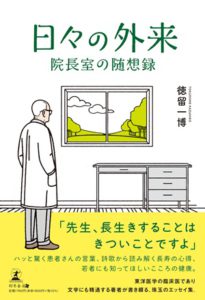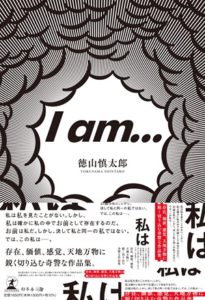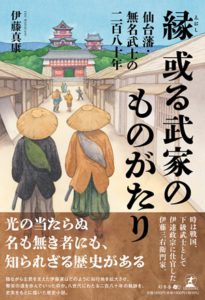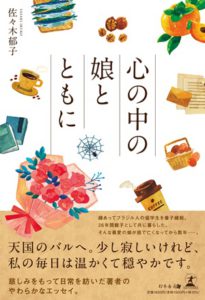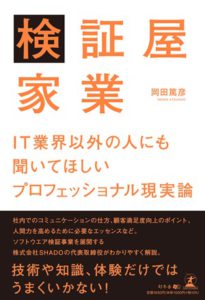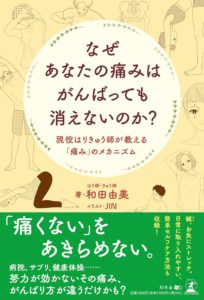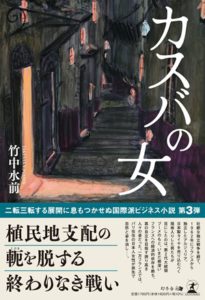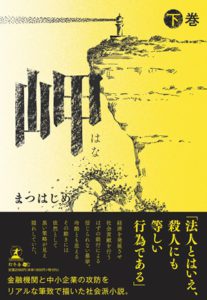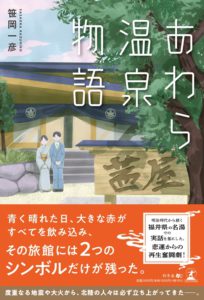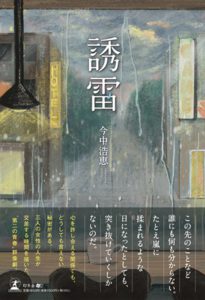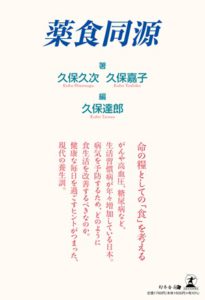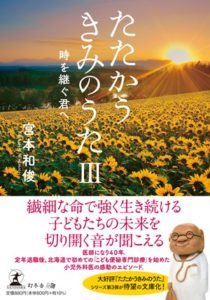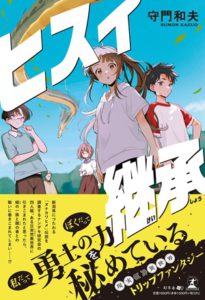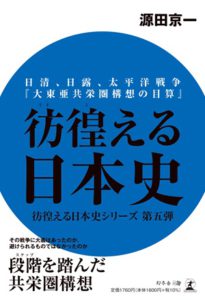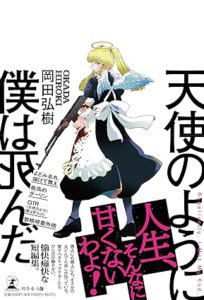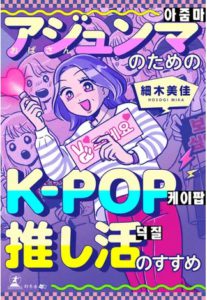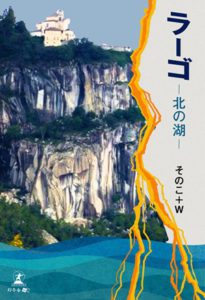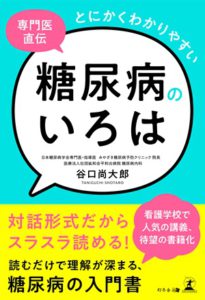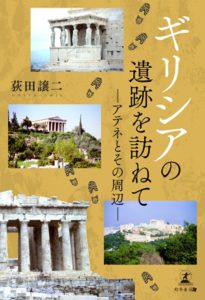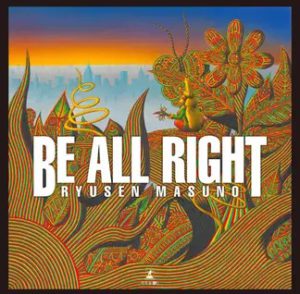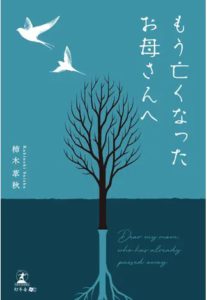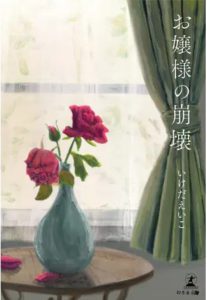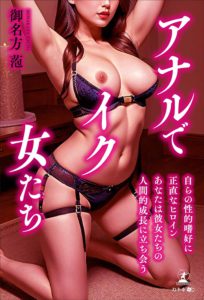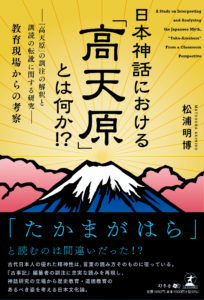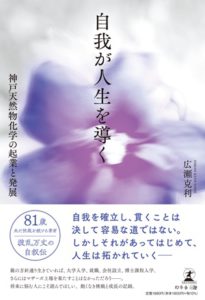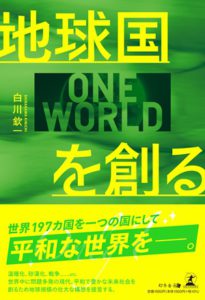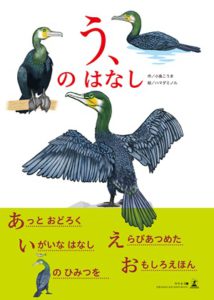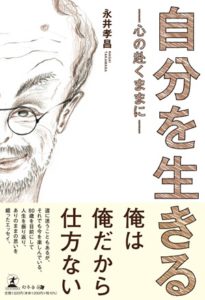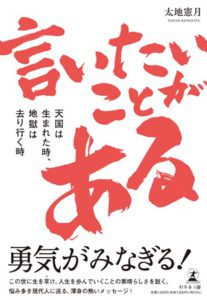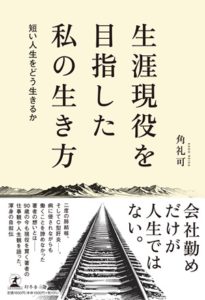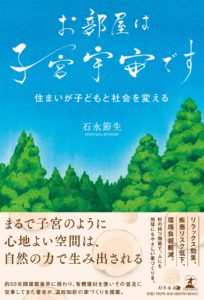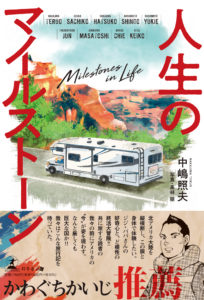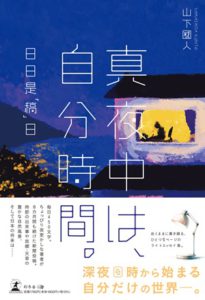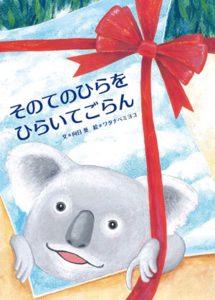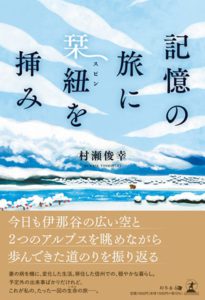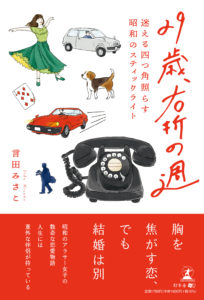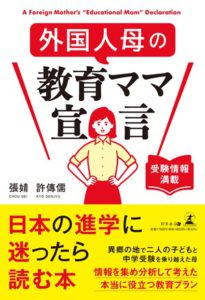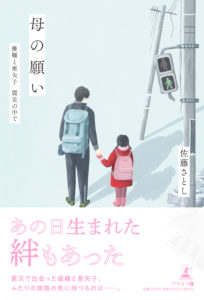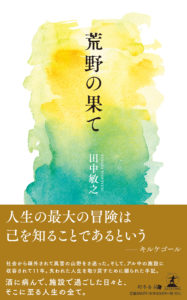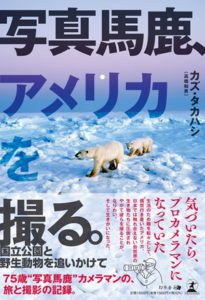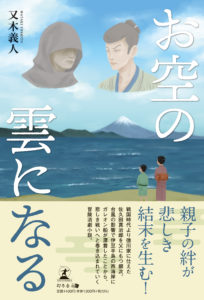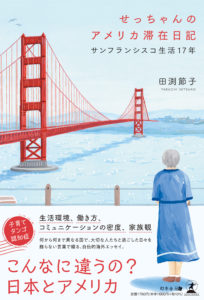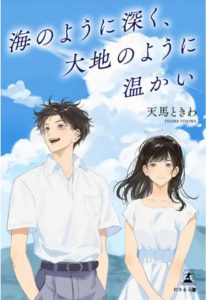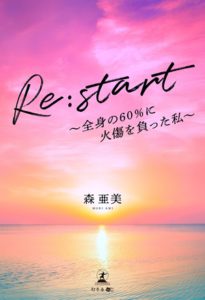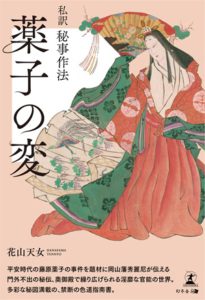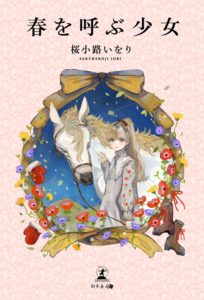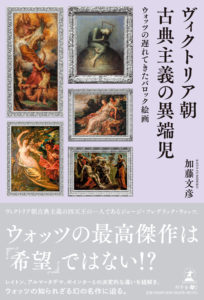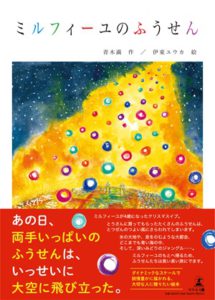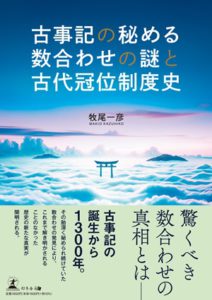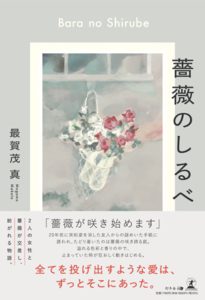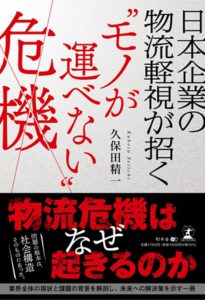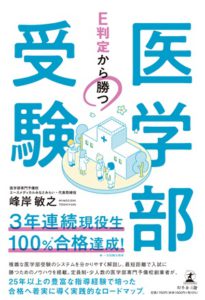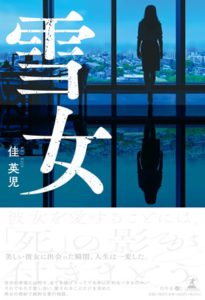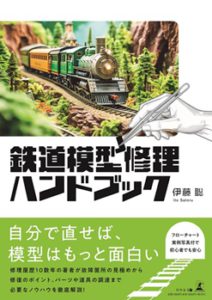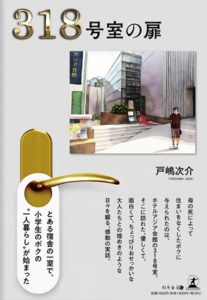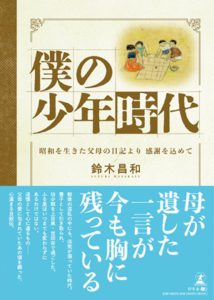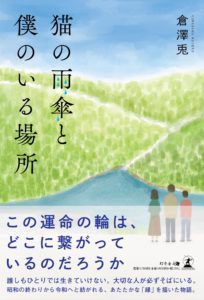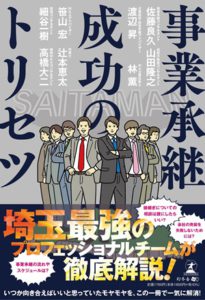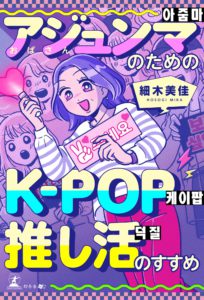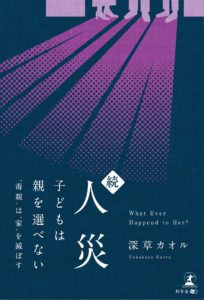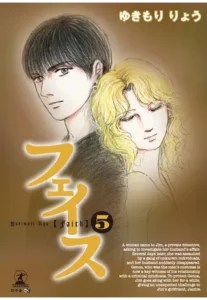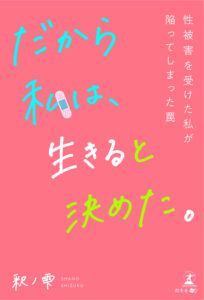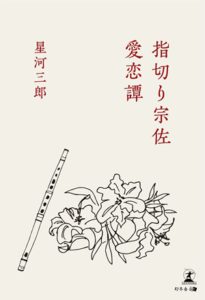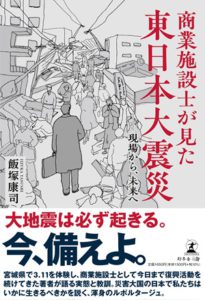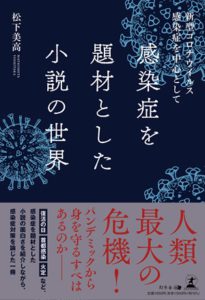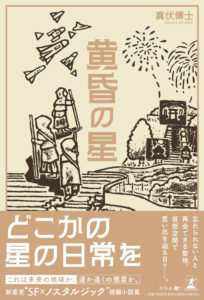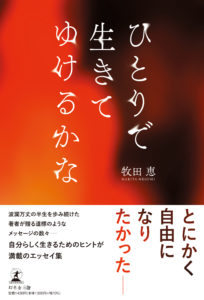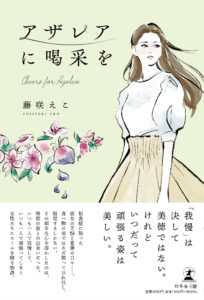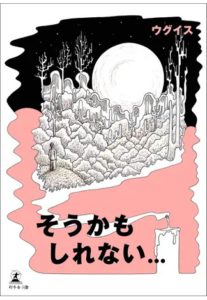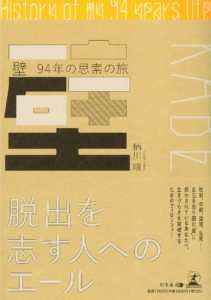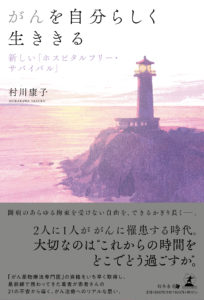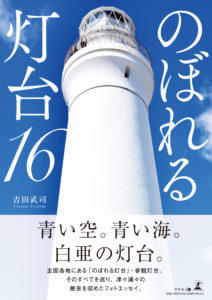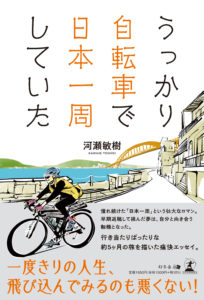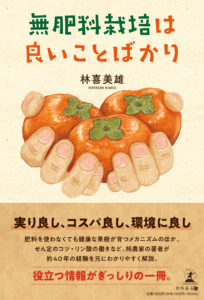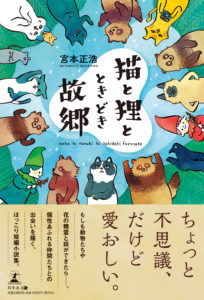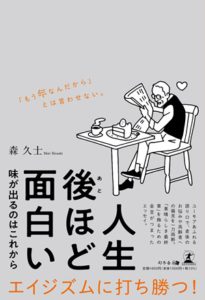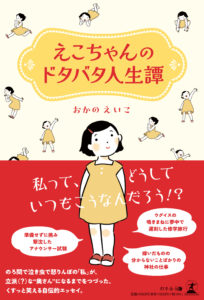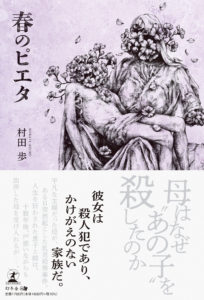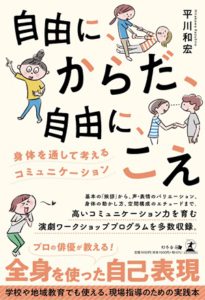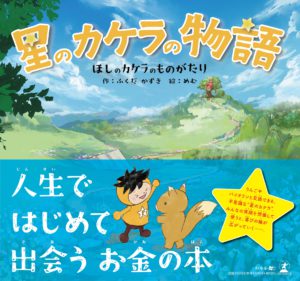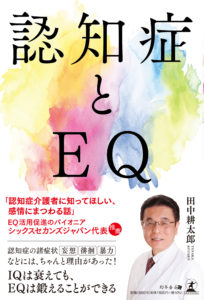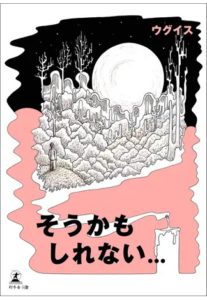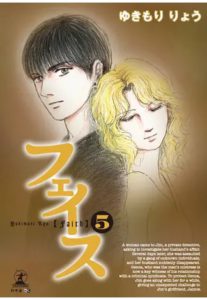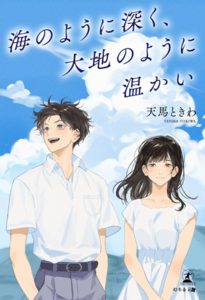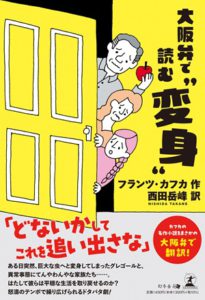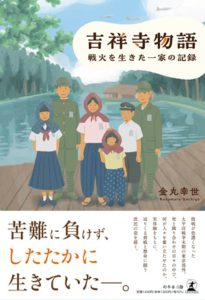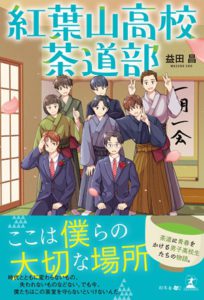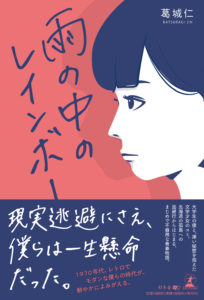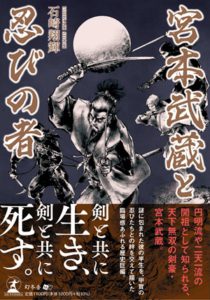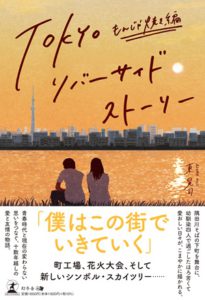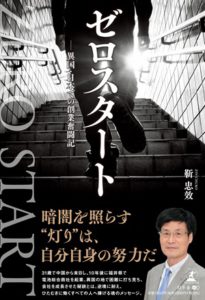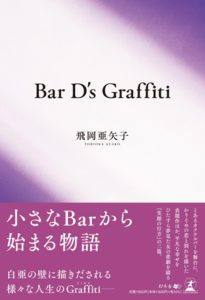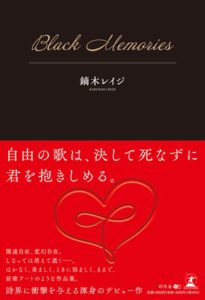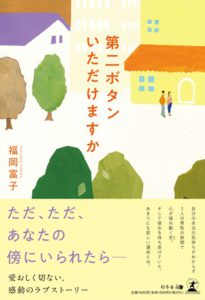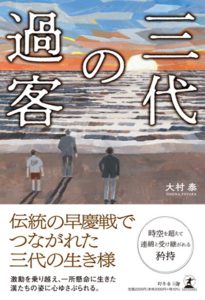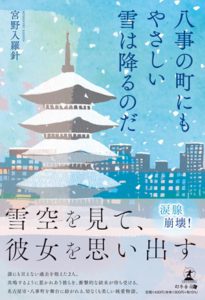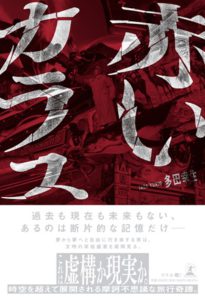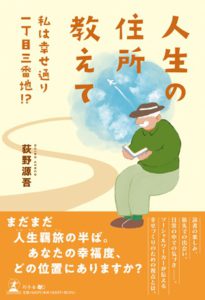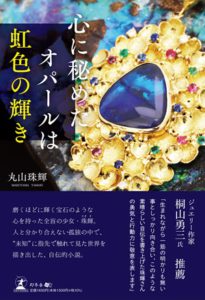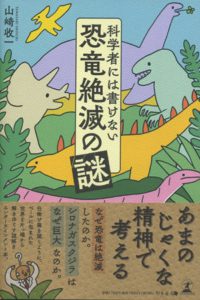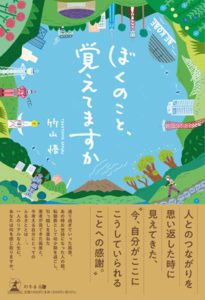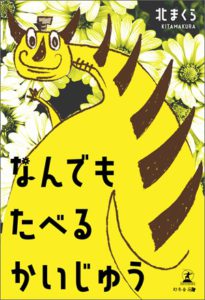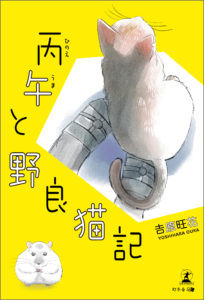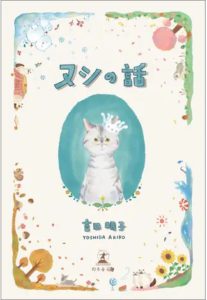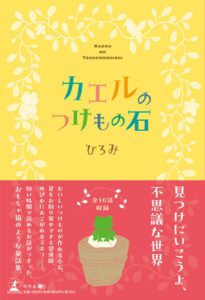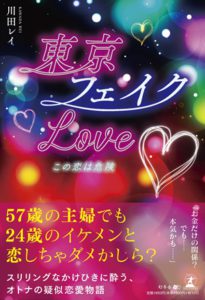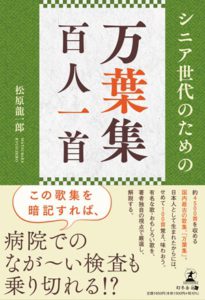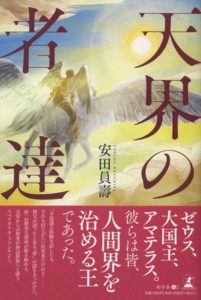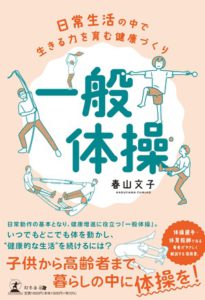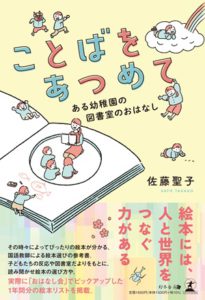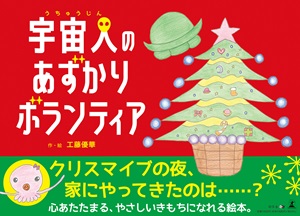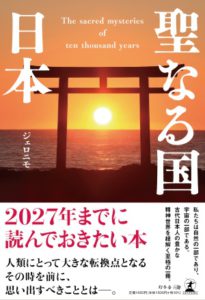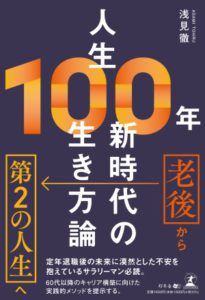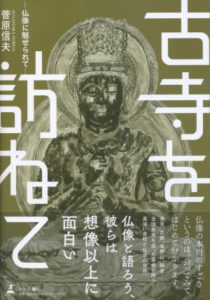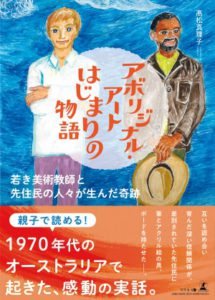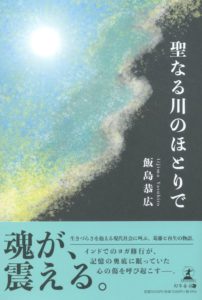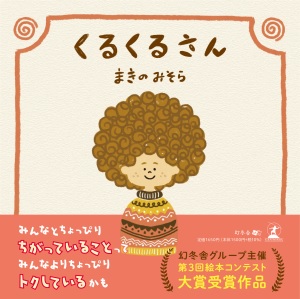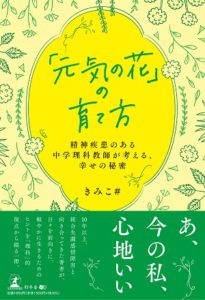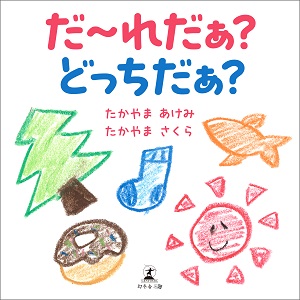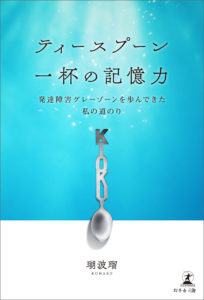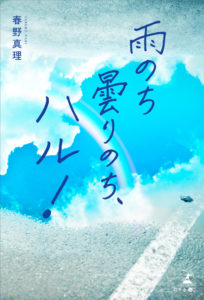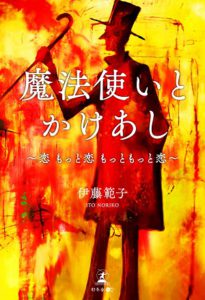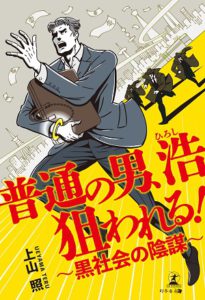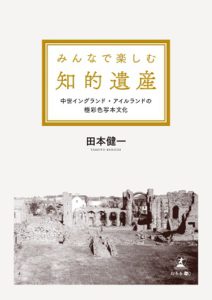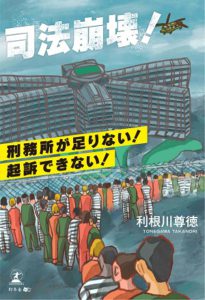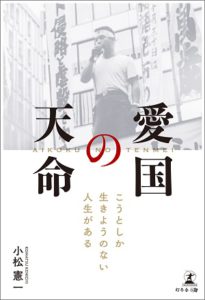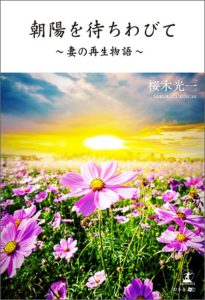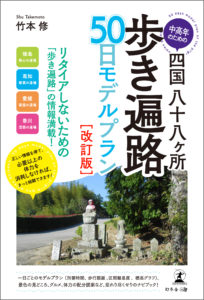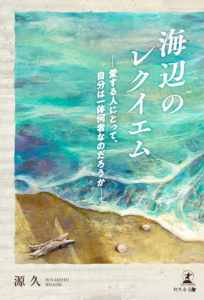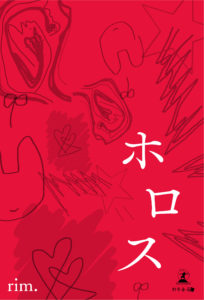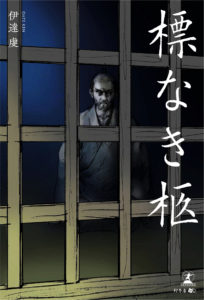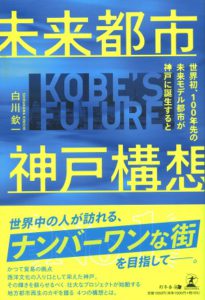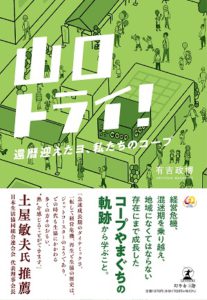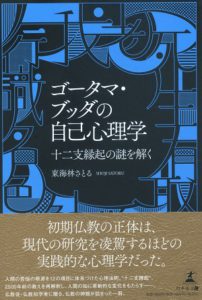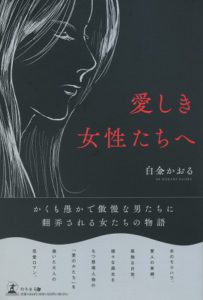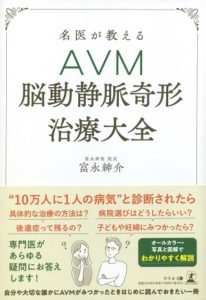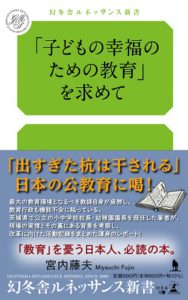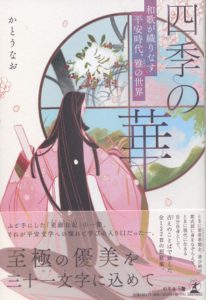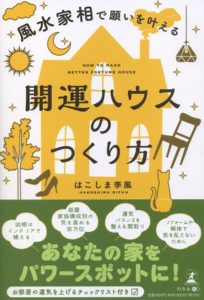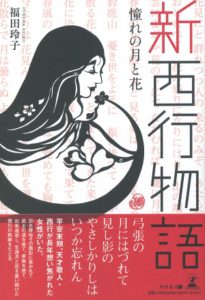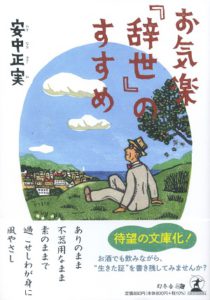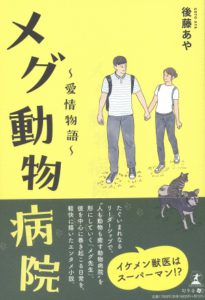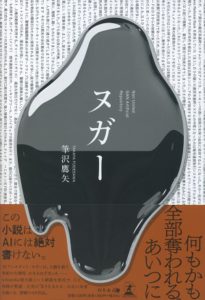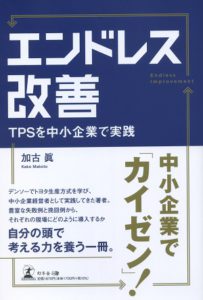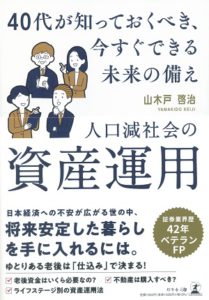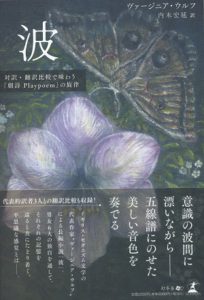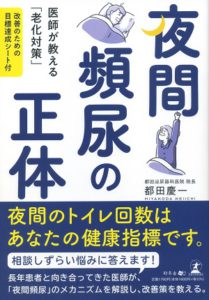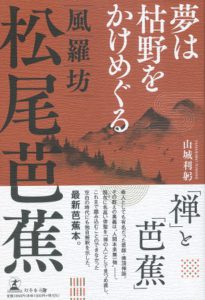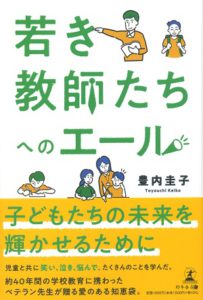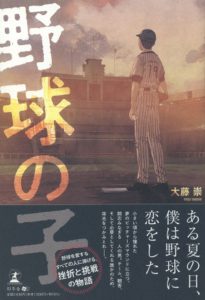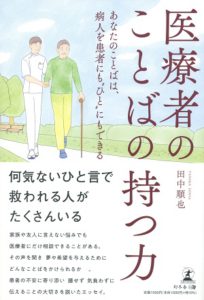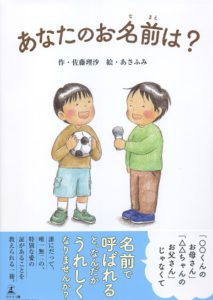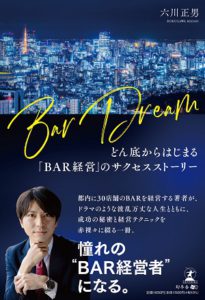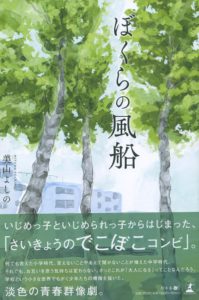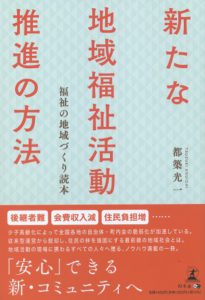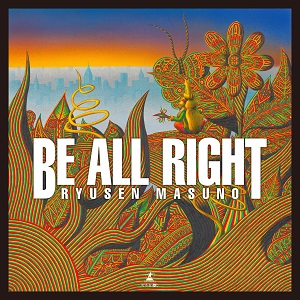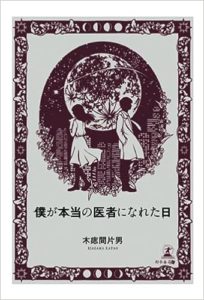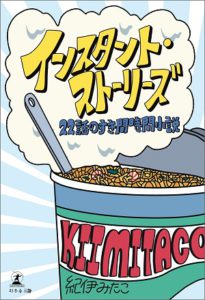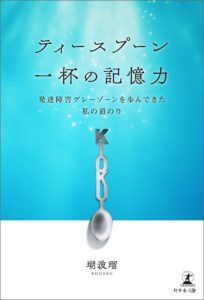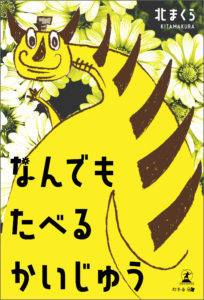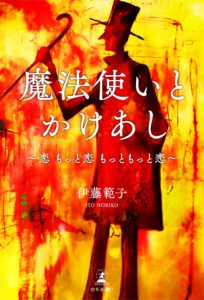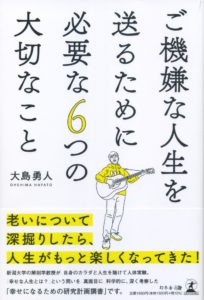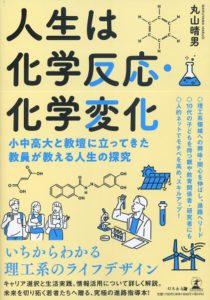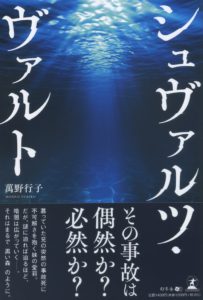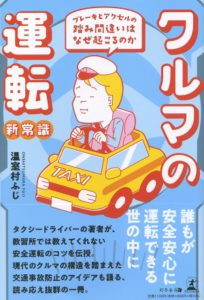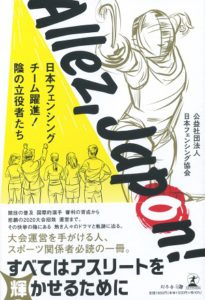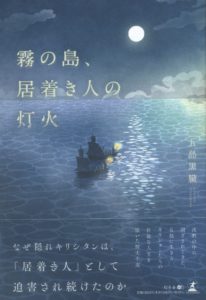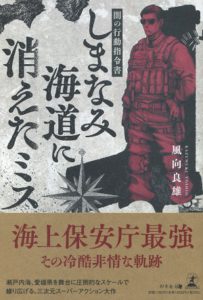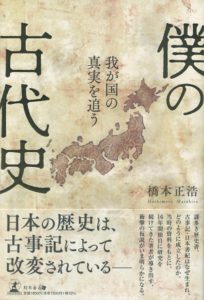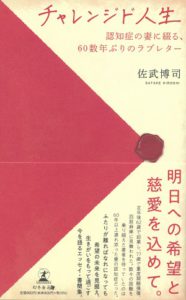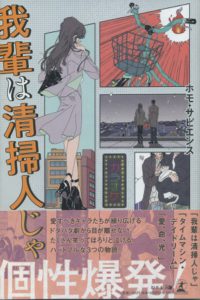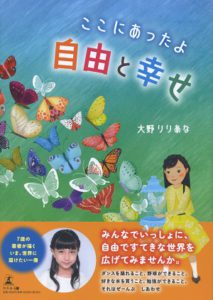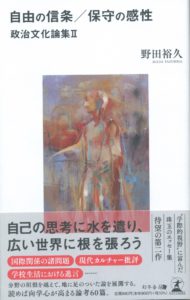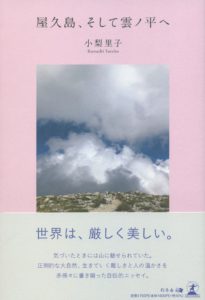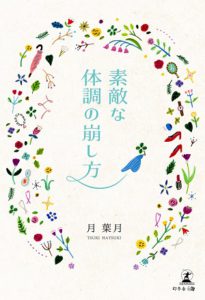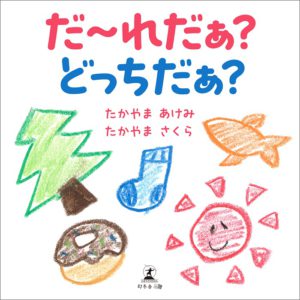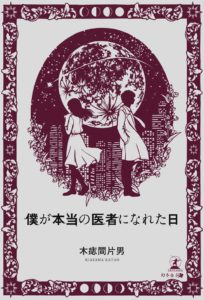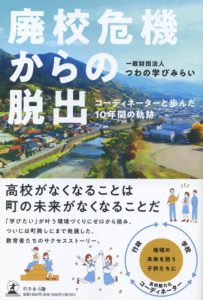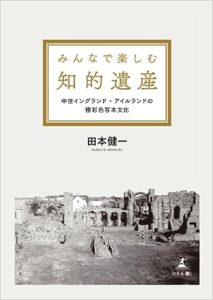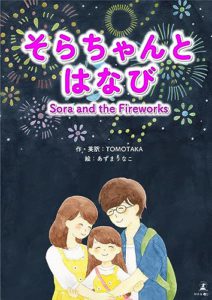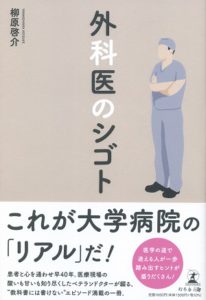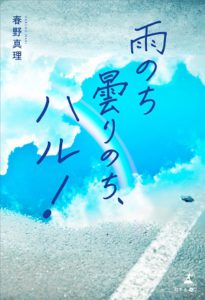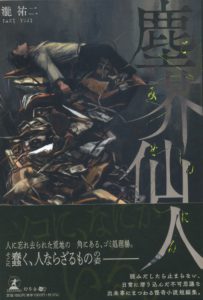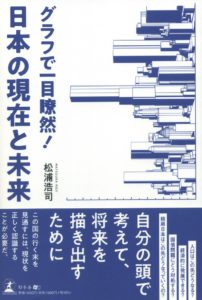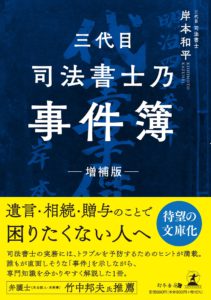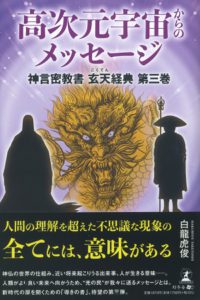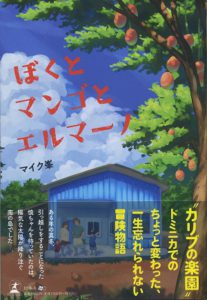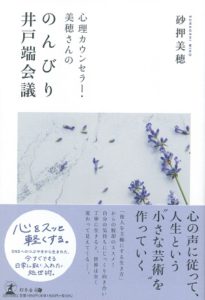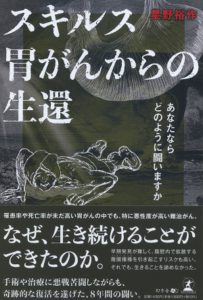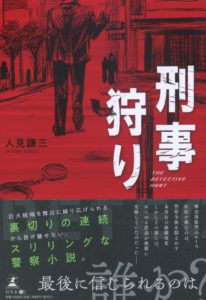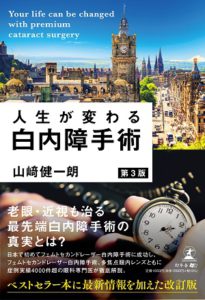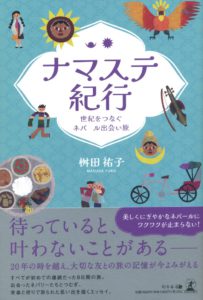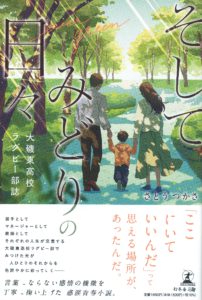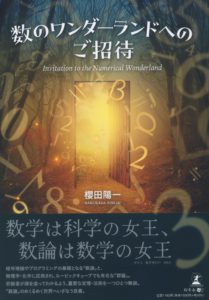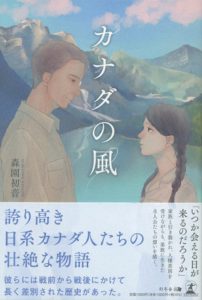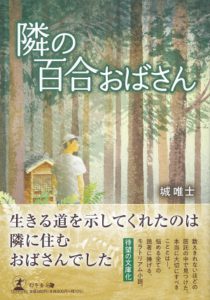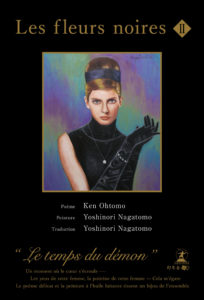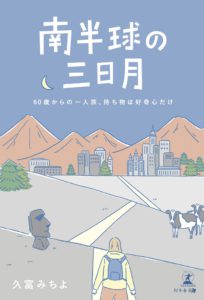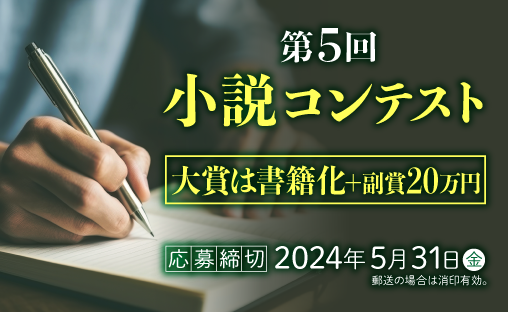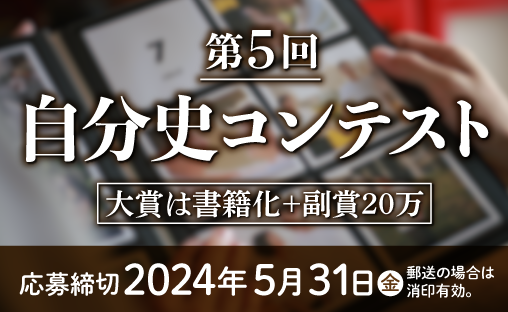出版サービス
説明会情報
一覧はこちら
-
相談会・出版説明会
原稿相談会・各種出版説明会
-
4/25(木)14:00~15:30 東京会場セミナー
「本を出版するまで、どんなプロセスがあるの?」
出版までの具体的なスケジュールを教えます!
出版実現セミナー -
4/30(火)11:00~11:30、15:00~15:30、 5/7(火) 11:00~11:30、15:00~15:30、 5/14(火) 11:00~11:30、15:00~15:30 他 東京会場説明会
小説出版説明会
-
4/24(水) 11:00~11:30、15:00~15:30、 5/1(水) 11:00~11:30、15:00~15:30、 5/8(水) 11:00~11:30、15:00~15:30 他 東京会場説明会
絵本出版説明会